みなさん,こんにちは,石尾です.
先日,9月29日(日)から10月5日(土)までパリに行っておりました.世界最大級の太陽光発電システムのカンファレンス,EU PVSECに参加するためです.
2年前,先生と二人のドクターの先輩にくっついて行って以来,2度目の参加です.今回は一人旅です.
というわけで,成田空港から約12時間かけてL’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle(シャルル・ド・ゴール国際空港)にやって参りました.直前までバタバタしていたため,ほとんど何の予備知識も無い状態での旅行です.
今回は,空港とカンファレンス会場の両方からほど近い,Premiere Classe Hotel, Paris Nord 2に宿をとりました.1泊€40程度と,パリにしてはかなりリーズナブルなホテルだと思います(ただし,朝食はパンとコーヒーのみ!).

シャトルバスで向かっても良いのですが,せっかくなのでホテルから会場までは歩いて向かいます.

パリ郊外は静かです.カンファレンスは8:30スタートのため,7:30には部屋を出るのですが,あたりは薄暗く,空気は冷たく湿っています.

道の至る所に大きなナメクジがいます.私の人差し指程度のサイズです.

ここから雑木林に入ります.

至る所に兎穴があるので,足元に気を付けなければなりません.そして,私の足音に驚いた野兎が何度も目の前を横切ります.

雑木林を抜けると,後は直進するのみです.

到着.
今回参加した、EU PVSECのプログラムは,①Keynote Speech,②Oral Presentation, ③Visual Presentation(ポスター発表),④Exhibition(企業等が行う展示・ワークショップ,商談),懇親会等のイベントで構成されています.参加者は,広大な会場を歩き回り,各所で開催されるセッションに自由に参加します.昼食時間や多少の休憩は挟むものの,8:30から18:30まで通して行われるイベントであるため,集中力を保つには努力が必要です.
発表内容は,①Material Studies, New Concepts, Ultra-High Efficiency,②Wafer-Based Silicon Solar Cells and Material Technology,③Thin Film Solar Cells,④Components for PV systems,⑤PV systems,⑥PV – a Major Electricity Source,と言った太陽光発電システムに関わる6つのフィールドに分けられ,発表者は分野ごとに割り当てられた会場で発表を行うことになります.
私の研究内容はPVシステムの劣化・故障や維持管理に関するものだったので,5番目の”PV Systems”に分類されました.
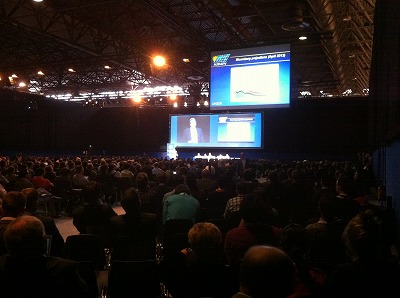
開会式の様子です.

そして,これが企業ブースです.
今回私が行ったのは,Visual Presentation,所謂,ポスター発表です.2日目の午後5時から6時半の予定で行われました.90分の間,ポスターの前に立ち,流れてくる参加者へ説明を行ったり質問に答えたりしなければなりません.
発表直前には,誰も来なかったらどうしようだとか,ひどい質問をされたらどうしようだとか,頭が真っ白になったらどうしようだとか,英語でうまくやれるだろうかなどと,色々な不安ごとが頭をかすめましたが,博士課程にもなると,さすがに鈍くなってきたのか,落ち着いてこなすことができました.
90分間で20人くらいの方が来てくださったのではないかと思います.色々とやり取りする中で課題も多々見えてきましたが,「面白いですね」等と言ってくださる人もおり,非常に嬉しかったです.
もっと殺伐とした雰囲気で,「やりあう」ものだと思い込んでいたのですが,違ったようです.もちろんそのような局面もあるのかもしれませんが,プレゼンの後は,ざっくばらんに意見交換をし合うといった感じで,かなり楽しめました.
その夜は,会場近くのレストランでタルタルステーキを食べました.

発表が終わってからは,余裕も出てきたため、他のポスター巡りやOral Presentationを巡りをします.主に,信頼性評価や劣化故障について,独立型システム・蓄電池について,発電量予測や制御について,市場や将来予測についての研究を中心に巡りました.
特に,PVが原因の火災に関する研究や砂漠地帯における運用,開発途上国の未電化地域における独立型システム運用の経済評価等に関する研究が印象的でした.
ドイツ国内だけでも,これまで180件のPVシステムに起因する火災の発生が確認されているそうです.日本国内でも火災の発生は確認されているようで,大量導入の進む今,適正な回路設計,モジュール材料の選定,保守点検の重要性はますます高まっているのではないかと感じました.
また,未電化地域におけるPVシステムの運用の際には,経済的理由により劣化した蓄電池の更新が滞ってしまうという問題に直面するケースが多く.打開策も見い出せていない状況にあるとのことでした.阿部研OBのWilliamさんの活動のように,地域によっては,PV「システム」にこだわらず,ニーズを踏まえたうえで,使用する技術を使い分けていく必要があると感じました.

5日間はあっという間でした.「ようやくフランスに慣れてきた」というところで閉会式です.
今回このカンファレンスに参加し,PVシステムの現状についての全体像を少しはつかむことが出来たのではないかと感じています.
今回のカンファレンスで,まず,最も目を引いたのが,豊富な日射量を確保することのできる赤道地域への導入を想定した研究が2年前よりも多く見られた点です.砂漠地帯や南の島々での日射量予測・発電量予測や,モジュールやシステムの劣化・不具合,そのメンテナンス法,産油国への導入可能性等,に関する研究が数々見受けられ,今,新たな導入先として赤道地域が注目を集め始めていると感じました.今後,果たして導入は進むのか,課題は多々ありそうですが,私も注目していこうと思います.アルジェリアの研究者が「うちの国では無理だ,FITも無いし...理由は,色々だ」と言っていたのが印象的でした.
次に,これまで,PVシステムの強力な導入阻害要因は高いコストにあると言われていましたが,低価格化やFITの導入等が進み,導入量が増加した結果,現在新たな導入阻害要因として系統連系に関する問題が今まで以上存在感を増しているようです.周波数安定化に関する技術的・社会的研究が複数見られました.特に,蓄電池の導入は系統安定化対策のための重要な技術的解決策のひとつであるため,蓄電池市場の規模は,2017年には,1兆400億円規模にまで成長する見通しだそうです(2012年時点では200億円規模だそうです).
そして,閉会式では,「PVシステムは,これまで技術主導型のプロダクト・イノベーションが行われてきたが,今後は市場主導・ニーズ主導型のプロダクト・イノベーションに徐々に切り替わっていくのではないか,また,技術開発により,高効率化,低コストが進んだ今,インセンティブ制度無しでもPVシステム市場は自立的に成長していくのではないか」との見通しが語られました.その中では,O&M(維持管理・保守点検)の重要性についても触れられており,やる気が出ました.
閉会式は午前中で終了しました.帰りの便は翌朝だったため,午後は市街地観光に充てました.とは言っても,大した時間も予算も無かったので,ルーブル美術館1本に絞って攻めることにしました.
最寄りの駅から1度乗り換え,30分程度でしょうか,オペラ座近くの駅に到着します.そこからしばらく歩くと到着です(大雑把に地図を見て降りる駅を決めたので結構歩きました).
有名なピラミッドですね.入り口付近で持ち物検査があります.
中はこのようになっています.入場料は常設展?と特別展?併せて20ユーロ弱でした.
すごい作品はいろいろとありましたが,私が特に気に入ったのは,この皿です.オスマントルコでつくられたイズニーク陶器ですね.15~17世紀ころの作品が多かったような気がします.
美術館全てを見て回るには圧倒的に時間が足りませんでした.足の裏が痛くなってきて帰ろうと思っていたころになって,ようやくの対面です.あの,モナリザです.「『意外と小さかった』,と言うほど小さくもないなあ」等と思いながら,じっくり見ようと思いましたが,シャッターを切る観光客のあまりの多さと歓声のうるささに気が散ってしまい30秒程度で退散です.絵画は静かに鑑賞するに限ります.
今度は,数回に分けて来ようと思います.
ポン・デザール(芸術橋)からセーヌ川を眺めます.これをパリの思い出に,再び12時間かけて帰国しました.
今回,このような機会をくださった阿部先生,手続等をやってくださった坂本さん,そして,現地で良くしてくださったみなさま,ありがとうございました.



