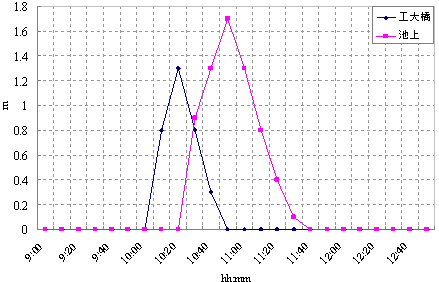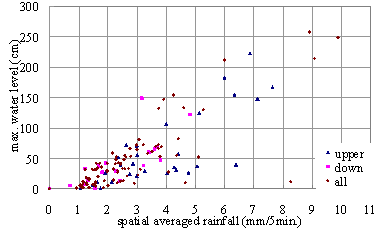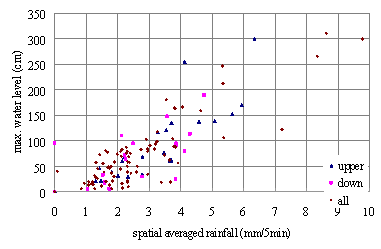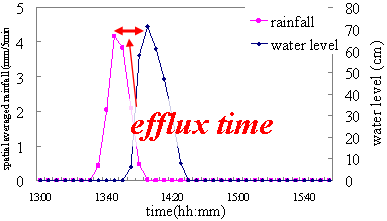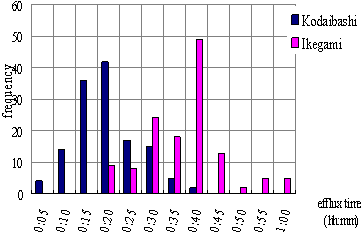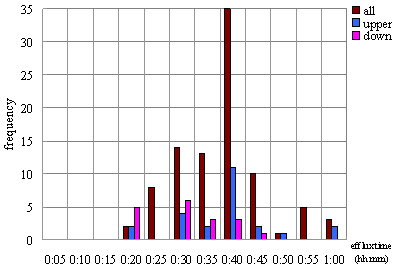平成20年7月には呑川上流域での集中豪雨によって生じた突発的水位上昇によって、河床作業中の作業員が流され、お亡くなりになるという痛ましい事故が起こりました。図1a はその時の工大橋水位計及び池上水位計の観測値です。(事故現場は工大橋と池上の間の比較的池上よりです。)水位上昇開始からわずか数10分の間に最高水位が記録され、その急激さがうかがわれます。
このような呑川の流出特性を把握することは、呑川における作業の安全性確保に資するだけでなく、呑川の生態環境改善のためにも重要です。本解析はそのようなことを背景と及び目的として行ったものです。
|
|||||||||||
解析に使用したデータは2000年〜2007年の間に東京都建設局河川部によって計測されたものです。雨量データは図2中の赤点で示した9雨量観測所のデータを、水位データは先述のように工大橋、池上での観測データを使用しました。すべて観測時間間隔は1分です。 今回はこのデータを用いて、観測点からの距離による重み付け平均によって集水域平均5分間雨量を計算し、使用しました。水位データも5分間隔に間引きをして使用しています。 |
|||||||||||
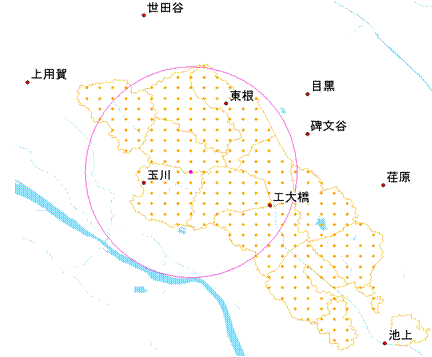 図2. 雨量観測所と水位観測所 (黄色の点は観測点から距離による重み付け平均で集水域域平均雨量を求める際に使用した点を示し、ピンクの円はその探索半径です。) |
|||||||||||
図6を見ると、工大橋での流出時間は20分、池上では40分ということがわかります。 池上では工大橋と違い、流出時間のピークが2つ存在します。 図7は、池上の流出時間と頻度の関係です、凡例にあるように、こげ茶色が集水域全体での降雨イベントを示しており、以下青が上流域、ピンクが下流域です。青とピンクを比べると、青は流出時間40分で最大頻度を迎えるのに対し、ピンクは20分から30分の間に最大頻度を迎えます。 これは、下流域の降雨が、池上の観測所に近いことが原因です。 このように2通りの流出パターンが存在するということは、 呑川流域規模の空間的広がりにおいて、降雨のパターンが2通り存在するということを示していると考えられます。 もちろん、流出経路の違い(下水道幹線を通るのか、直接呑川流入するのか)という原因が考えられますが、 現時点においては、降雨パターンの存在の可能性を指摘することとします。 詳細については、今後の流出解析で検討していきたいと思います。
|
使用データ (描画:ArcGIS9.2)
数値地図 5mメッシュ(標高) 東京都区部 国土地理院、 数値地図 2500 (空間データ基盤) 関東-3 国土地理院
集水域マップ
データ提供:東京都土木技術センター
厚く御礼申し上げます。