善福寺川取水施設見学 (2008年9月8日更新)
去る8月25日水文水資源学会総会に先立って開かれた、第8回水文・水資源に関する実務・技術部門交流会で、
善福寺川取水施設の見学が行われました。今回はその様子と紹介します。
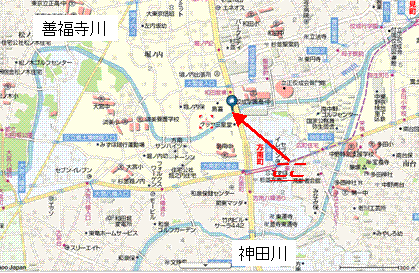
この施設は、水害が多発する神田川流域の安全向上のため計画された環七地下河川の一部である、神田川・環状7号線地下調節池を構成する調節池です。
神田川、善福寺川の洪水約54立方メートルを貯留することができるということです。詳しくはこちら。
見学の前に、簡単に施設の説明を受けました。

いざ、調節地へ。階段とエレベータがありましたが、その深さを実感するため階段を選択しました。
| 目指すは地下57m。 地下へもぐるとだんだん寒くなってきます。 |
|
| 調節池の中へ。 |
↓この穴から、善福寺川の水を取水します。写真でみると小さいですが、かなりの大きさでした。
この時、地上では小雨が降っており、わずかながらこの穴から水が入ってきていました。普段は完全に取水口を閉めている
ということでしたが、ここで大雨が降ったらと思うとこわいものです。この穴から入った水は、管↓を通ってさらに奥へと流れます。
行き着く先は、こちら。内径12.5mもあります。トンネルの中は電気設備がないため、真っ暗です。先のほうは見えません。
 |
施設の方のお話では、温度は常に変わらないようです。また今回はいつもより |
トンネル内に取り込んだ水は、ここ↑から晴天時にポンプアップされて川へ戻されます。
川の水を取り込むということで、どじょうなどが紛れ込むことが多いようです。(実際、今回もいたみたいです。)なんともかわいそうです。
写真ではトンネル内は大変きれいに見えますが、清掃後ということでした。やはり、取水後は砂等が堆積するみたいです。10cm程度になるとか。
それにしても、すごい規模の施設です。数十分見学の後、施設を離れました。
施設は、大変すばらしく頼れるものであると感じました。
しかし、このようなものを建設しなければ生活を守ることができないという現状にすこし違和感を覚えます。
出水時に流され、地下河川へとたどり着いてしまう魚のことを考えても、各戸貯留など流出抑制が重要であると感じました。
水文水資源学会 企画事業委員会実務・技術部門小委員会のみなさん、貴重な経験をさせていただいてありがとうございました。
Home